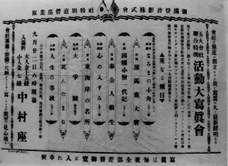木町(賑町)に中村座が開業
 中央西のそば店「おお西」は旧遊郭の離れ座敷。 当時の様子を残す記帳な遺構 |
唱歌の行路は活気づく官公庁街や文教地帯を離れ、町の北部へ進み木町、紺屋町、鎌原へと向かう。
木町と紺屋町を結ぶ木町街道(賑町)が開かれ、その中程、現在の中央四、上田製菓あたりに、芝居小屋の中村座が明治七年に開業した。花道のある演劇上として注目され、浪花節、演劇、落語等の興行に多くの人が繰り出した。賑町の名の由来もうなづける。
また、来田した内村鑑三もキリスト教の布教演説にこの館を利用している。
明治二十年頃になると、末広座、丸山亭など演劇上が続々開業、同三十年代になると活動写真もお目見得、映画を説明する弁士たちの名台詞に我を忘れ、またたく間に庶民の新しい娯楽として定着していった。
末広座は大正六年、現在の上田映劇の前身である上田劇場となり、上田電気館は、同十年映画常設館としてオープン、今も市民に親しまれている。
新しい時代を迎えたとはいえ、上田の町は城下町当時の呪縛からなかなか抜け出せず、その外濠である矢出沢川の外に町が発展していくのはたやすいことではなかった。
紺屋町あたりの北国街道を歩いてみても、川の対岸は二、三の水車小屋の向こうに呈蓮寺、海禅寺、八幡神社などの寺社が点在するだけで、桑園と水田が広がっていた。
ところが、この町から隔絶した田んぼの真中に明治十一年、様々な論議を呼びながら、江戸吉原風の遊郭が設置された。
やがて鉄道の開通や上田橋の完成でにわかにさびれだす北国街道沿いだが、遊郭の出現により鎌原一帯は飲食店や新しい諸商店が並び技芸の専修学舎も置かれ活況を示した。
遊郭への直線道路もあき、明治二十三年、その入口の浮世橋は土橋から木橋に改修され同三十年頃には二十八軒の楼、娼妓は約二百人に達し、多い月には約一万人の客があったという。
途中、廃娼運動も盛んになったが、盛況は大正時代も続いた。